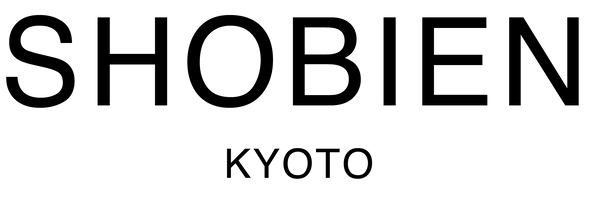コンテンツにスキップ
ろうけつ染め
日本のろうけつ染めの歴史
染色は大陸(中国)から伝来した奈良時代にまで遡ります。ユネスコ世界遺産に登録されている奈良・正倉院には、「天平の三結地」と呼ばれる3つの染色技法が保存されています。臈纈(ろうけち)、夾纈(きょうけち)、そして纐纈(こうけち)です。これらの技法は後にろうけつ染め、絞り染め、板締め染めへと発展し、日本全国で広く愛され、受け継がれてきました。

当工房では、手描ろうけつ染め、型染めろうけつ染め、蝋吹雪染め(ろうふぶき)の3種類のろうけつ染め技法を用いています。手描ろうけつ染めと蝋吹雪染めは、着物や暖簾の染色に特に人気があります。また、当工房創業者の勝美が提唱した型染めろうけつ染めは、暖簾やインテリア、ファッションアイテムなど、単幅の生地に幅広く活用されています。
ろうけつ染めは、複雑なひび割れ模様、繊細な蝋飛び模様、優美で流れるような線などが特徴で、現在でも愛されている伝統的な染色技法です。
手描きのろうけつ染め

手描きろうけつ染めは、熱した蝋を刷毛で直接布地に塗りつける染色技法です。蝋で覆われた部分は染料が染み込みにくく、染色後に蝋を剥がすと布地本来の色が浮かび上がり、繊細な模様が生まれます。職人が一筆一筆丁寧に蝋を塗り込み、柔らかな曲線や繊細な模様を描き出します。主に特注の暖簾などに用いられます。

蝋吹雪染め

ろうぶぶきは、溶かした蝋を刷毛、竹筒、あるいは専用の道具を用いて布地にランダムに飛び散らし、独特で自然な斑点模様を生み出す染色技法です。その模様は、不規則でありながらも視覚的に魅力的なモチーフが特徴で、有機的で自然な外観を呈します。SHOBIENでは、刷毛だけでなく、専用の蝋吹きスプレーも使用することで、雪の舞いのような自然現象を彷彿とさせる、より深みのある豊かな模様を生み出しています。

型を使ったろうけつ染め

型ろうけつ染めは、しょうび苑の創業者である勝美によって考案された、広幅(110cm)の蝋引き染めに特化した技法です。伝統的な型染めの技法をろうけつ染めに融合させたこの高度な技法は、複雑な模様や繊細な表現を可能にしました。幅80~110cm、長さ25mを超える、壁紙、反物、暖簾といった大型の織物用途に特化した、京都ならではの革新的かつ独自の技術です。


- 選択内容を選択すると、ページ全体が更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。