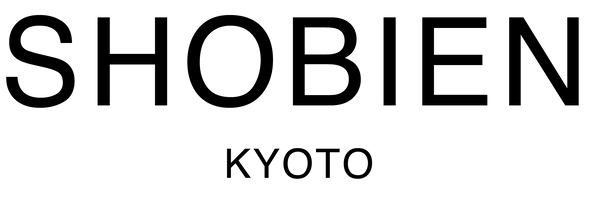暖簾
暖簾は、衝立、看板、間仕切りといった実用的な役割を担うだけでなく、日本特有の「間」の美意識を体現し、独特のコミュニケーション媒体としても機能しています。本稿では、暖簾の古代の起源から現代に至るまでの変わらぬ歴史を辿ります。

暖簾の起源
奈良時代と平安時代、貴族の邸宅や仏堂には、隙間風や埃を防ぐため、 「垂れ布(たれぬ)」または「御簾(みす) 」と呼ばれる布が掛けられていました。これらの初期の形態が、今日の暖簾のルーツです。通気性に優れた苧麻(ちょま)で織り、植物由来の単色で染められた暖簾は、日光や砂埃を遮るだけでなく、室内の生活が「見えすぎる」ことを防ぐ半透明の境界としても機能していました。

中世から江戸へ ― 商人の軒先から家庭の言葉へ
室町時代に入ると、これらの布は貴族の屋敷を離れ、商家の軒下にも見られるようになりました。紋や屋号などが染め抜かれ、店の開店時には掲げられ、閉店時には畳まれる看板のような役割を担うようになりました。この頃から「暖簾」という言葉が一般的になり、守る(遮蔽)、知らせる(営業時間を示す)、そして呼び込む(ブランド化)という三位一体の機能が確立されたのです。

現代 ― 染色革命とデザインの多様性
明治時代以降、合成染料の登場により多彩な色彩表現が可能になり、厚手の帆布や綿布が町家、旅館、銭湯などにも普及しました。商店間の競争により暖簾は広告媒体となり、鮮やかなグラフィックとキャッチーなキャッチコピーで路地裏を明るく彩りました。素材の改良により断熱性や耐火性も向上し、実用性とデザイン性のバランスが深まりました。